現場崩壊が生む悲劇:「合理的配慮」が娘に届かなかった理由
あの、取り出し授業をしている短い一瞬、
30人のこどもを連れて移動している担任の先生が
娘に向けたあのまなざしを、私は今もはっきりと覚えています。
娘をちらりと見たきり、声をかけることなく、
そのまま通り過ぎていくその姿。
それは、「もうはみ出てしまった子は、対応できません」と、
無言で告げているように見えました。
その時、私には学校現場の極限の現実が見えてしまいました。
30人というクラスの中には、発達傾向にある子が3〜4人はいる。
中には、他害行為や教室からの脱走など、
目を離せない行動をとる子もいる。
担任の先生は、常時体制で対応する支援員とともに、
その命や安全に関わる緊急性の高い対応に追われ、
疲弊しきっていました。
参観日に訪れた際も、
支援員は常に特定の子のそばを離れず、
娘が寂しそうにしているのを見ても、誰も声をかけてはくれませんでした。
もし私が担任の立場だったら、きっと同じように、
緊急性の低い娘まで手が回らなかっただろうと理解できます。
理解はできる。しかし、感情は納得できません。
であれば、なぜ「合理的配慮」という言葉だけが、
まるで希望の光であるかのように制度として存在しているのでしょうか。
現場のリソースが限界を超えているのに、
「個別対応が可能です」「誰も置き去りにはしません」と、
保護者に期待を持たせる仕組みは、むしろ残酷な偽善ではないでしょうか。
制度は、人手や予算といったリソースの裏付けなしに、
理想だけを掲げている。その結果、一番苦しむのは、制度に期待し、叶えられない現実に直面する子どもとその保護者です。
娘に必要だったのは何だったのでしょうか。
どうしたら不登校にならず、楽しく通い続けられたのでしょうか。
パンク寸前の教育現場の壁の向こうに消えてしまったことが、
何より娘の心を深く傷つけたのだと痛感しています。


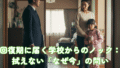
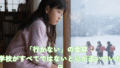
コメント