9月。
親子ともに、もう限界を感じていました。
それでもどうにか学校に通わせようと、
改めて支援級への転籍を打診しました。
けれど、支援級の都合で体験はすぐには受けられず、
その間も、教室での毎日が続きました。
「座っているのがつらい」と長女は言いました。
少しでも落ち着いて過ごせるようにと、
机の脚にはゴム状の感覚刺激グッズをつけてもらい、
お尻が痛いというので、
特別にクッションも使わせてもらいました。
でも――もう、そういう工夫でどうにかできる段階ではありませんでした。
長女は徐々に、受けられない授業が増えていきました。
最初は国語と算数。
次に、せいかつ、体育、道徳。
そして最後に残ったのは、音楽だけでした。
10月に入り、特別支援コーディネーターの先生に相談し、
「取り出し授業」という形を取らせてもらうようになりました。教室を抜けて、別室でマンツーマンの授業を受ける形です。
対応してくれたのは、支援員の先生、コーディネーターの先生、
ときには教頭先生まで。
それでも、図工の工作でさえ教室で受けられなくなっていきました。
長女の中では、もう学校そのものが“つらい場所”になっていたのだと思います。
#不登校の記録#支援級への道#付き添い登校#登校しぶり#教室にいられない#取り出し授業#特別支援コーディネーター#母の葛藤#小1の壁#不登校ブログ#子どものペースで#限界を感じた9月

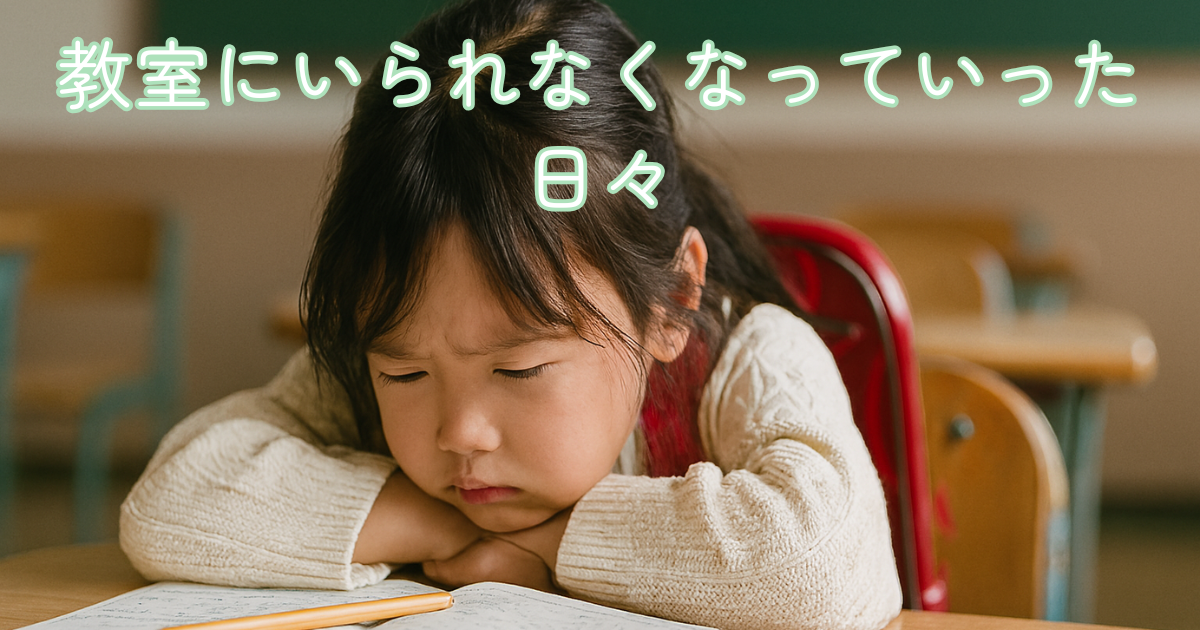
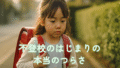

コメント